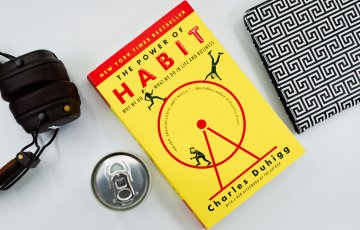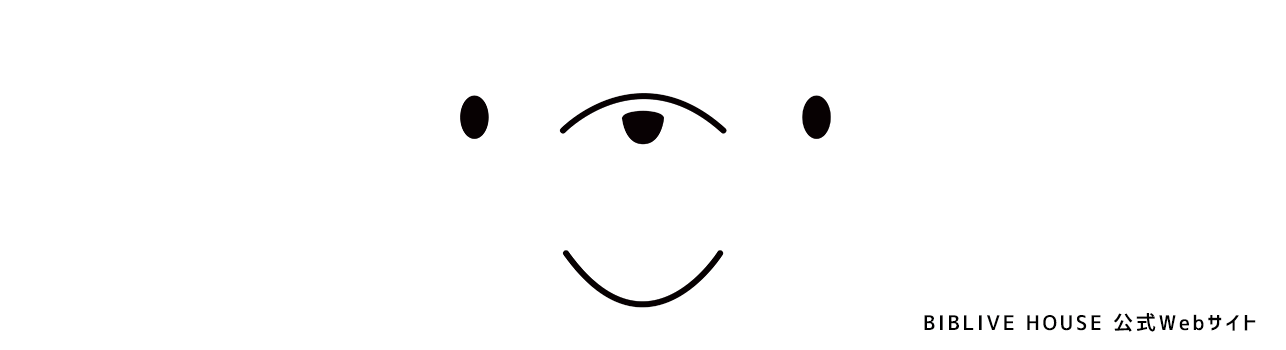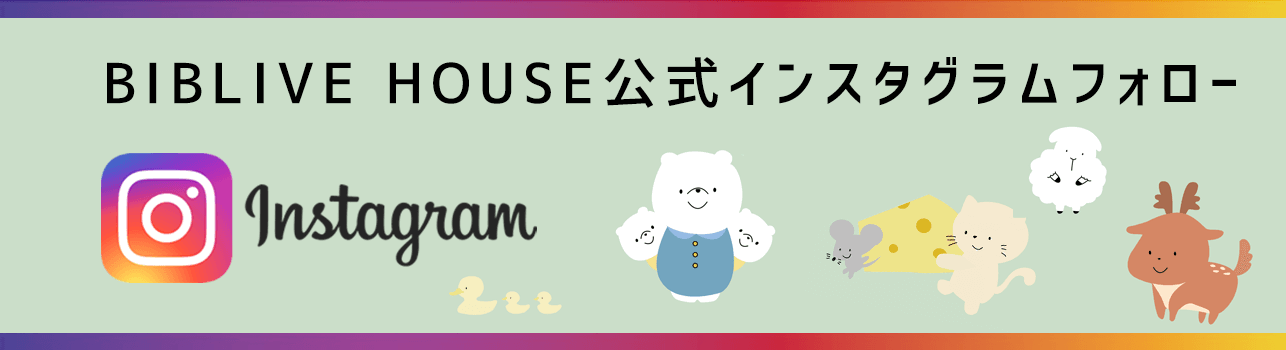両極端にふれ切る
最近、両極端にふれ切ることを繰り返すのは成長する上で非常にに大切だと思わされています。具体的に書きます。例えば、学生は部屋にこもって勉強ばかりするのではなく、時に勉強のことそいっそのこと忘れて思いっきり遊ぶことで勉強も効率的になるということです。これは仕事にも言えるでしょう。
この考え方はおそらく、多くの人も同意されるのではないかと思います。
活字への渇望
これは僕の経験に一致しています。たとえば僕の休日の1日の80%は家族や子供と過ごすことに集中しています。こどもが起きてからこどもが寝るまで自分の時間はありません。しかし、おおよそ21時以降から自分の時間が始まり読書を始めると飢えたライオンが獲物を食らう如く活字に対する異常な集中力が沸き起こります。
これのような現象は以前にもありました。新卒で入社したメーカーでは研修で1日中プレスを打ち続けるという作業を何か月も行っていました。1日8時間以上単純作業をするのですが、業務中での活字への渇望がすさまじいのです。一刻も早く活字を読みたいと思うのです。
ラベルの裏に書かれている活字
このようなことは確か「きけわだつみのこえ」にも書かれていたと記憶しています。学徒出陣で招集された学生が訓練や作戦に従事される中で、活字への渇望が起こります。普段の日常でゆっくり活字を読む時間は一切ありません。その人は、食堂にある醤油かなにかのラベルの裏に書かれている活字を隅から隅まで読んだと書かれていました。
もちろん、何の制約もなく自由に活字をいつでも読める状態はいいことかもしれません。しかし、この両極端に振れ切るというのを逆手にとって意図的に試みるのはいいことだと思います。
乾いたスポンジ
なぜなら、そのほうが明らかに吸収力が上がるからです。最近は中国から届いたレイダリオ氏の「How Countries Go Broke: The Big Cycle」という論文を中国語で読んでいます。論文を外国語で読むのは気力と集中力が要求されます。しかし、両極端に振れ切って渇望状態になっていれば、そういった気力や集中力を意識せずとも、乾いたスポンジが水を一滴も余すことなく吸収するが如く学ぶことができます。
これは読書に限らずあらゆる学習で応用できることだと思います。