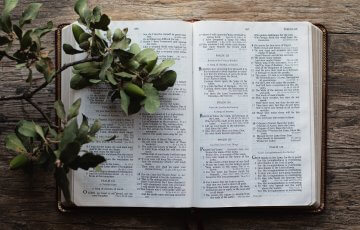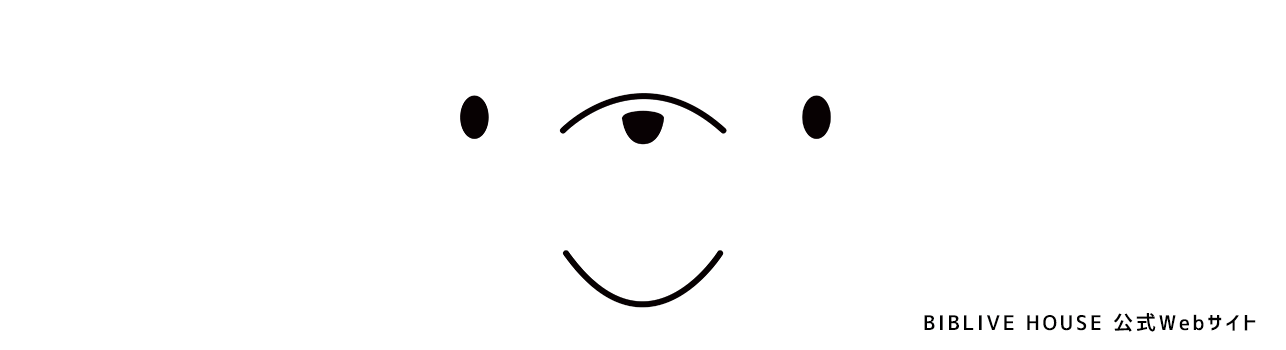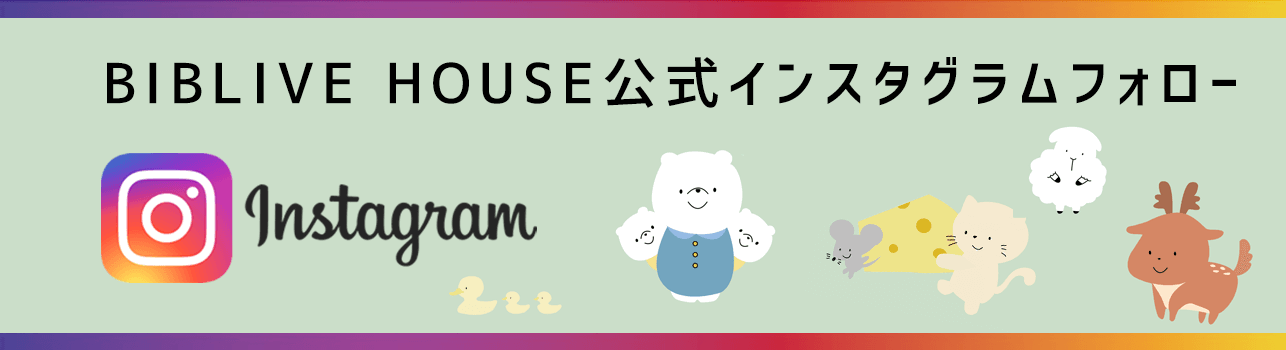祈っているのに敗走
昨日に引き続き士師記の最後の物語について書きます。
その後の結末はこのとおりです。イスラエルの11部族がベニヤミン族に対して戦争をしかけます。ここで理解に苦しむことがあります。それは、イスラエルの11部族は戦争の前に主に祈り判断を仰ぎ、主の命令に従って戦争を開始するにもかかわらず、イスラエルの民は敗走することになるのです。これはこれまでのイスラエルの必勝パターンに一致しません。
ベニヤミンの人々はギベアから出てきて、その日イスラエルの人々のうち二万二千人を地に撃ち倒した。
士師記20:21
途中で流れが変わる
その後も理解に苦しむことが続きます。イスラエルの民は再起を図るため主に祈り祭壇を築き断食までする覚悟でいます。そして主から「攻め上れ」との指示をもらったにもかかわらず、また30人あまりがベニヤミン族に殺されてしまうのです。そこでイスラエルの民は1万人の精兵を出します。ここからようやく流れがかわりました。
すなわちイスラエルの全軍のうちから精兵一万人がきて、ギベアを襲い、その戦いは激しかった。しかしベニヤミンの人々は災の自分たちに迫っているのを知らなかった。
士師記20:34
それからようやくイスラエルの連勝が続き、最終的にイスラエル軍はベニヤミン族を制圧することに成功します。これが士師記の最後に起きた物語です。
学べること
ここから何を学ぶことができるのでしょうか。士師記19章~21章は非常に難解で神学的な解釈や知識等が必要になるかもしれません。だから、僕は正確に何かを学び取ることはできないとも思っています。それでもいくつか考えたいと思います。
一つは、士師記はイスラエルの時代にとって暗黒の時代であったということです。道徳的にも相当堕落していました。これは2025年を生きる世界と全く同じだと思います。
信仰深いように見えるが
もう一つは主に祈り求めたイスラエルの民が敗走し続けたこと理由についてです。イスラエル11部族の最初の祈りでは「戦いに出ていいですか?」ではなく「どの部族が先に戦うべきですか?」と尋ねています。つまり、すでに戦う前提で祈っていたのです。これは彼らが神の御心ではなく自分の目的を果たすために祈っていたことの証拠です。
これは僕の推測にすぎませんが、神様は同部族内での争いに関して甲乙つけがたかったのではないかなと思いました。ベニヤミン族は確かに悪い。しかし、残りのイスラエルの11部族も五十歩百歩だったのではないかと推測されます。もちろん、イスラエルの民は戦争の前に神様を求めています。
しかし、もしかしたら、彼らは困った時の神頼みだけをしており、日々の生活では神様を疎かにしていたのではないか?というのが僕の推察です。ですから、この物語から学べることは、信仰深いように見えても、内実はそうかわからないということだと思います。これは僕にとって非常に耳が痛い指摘です。