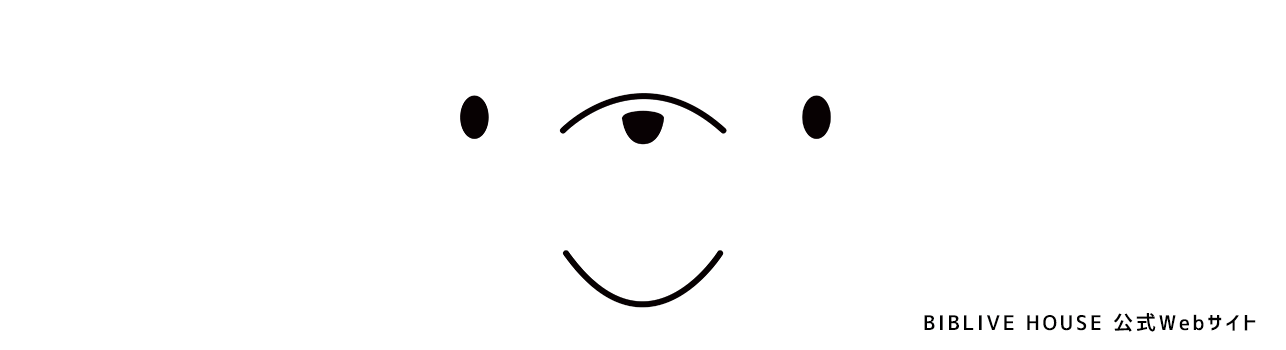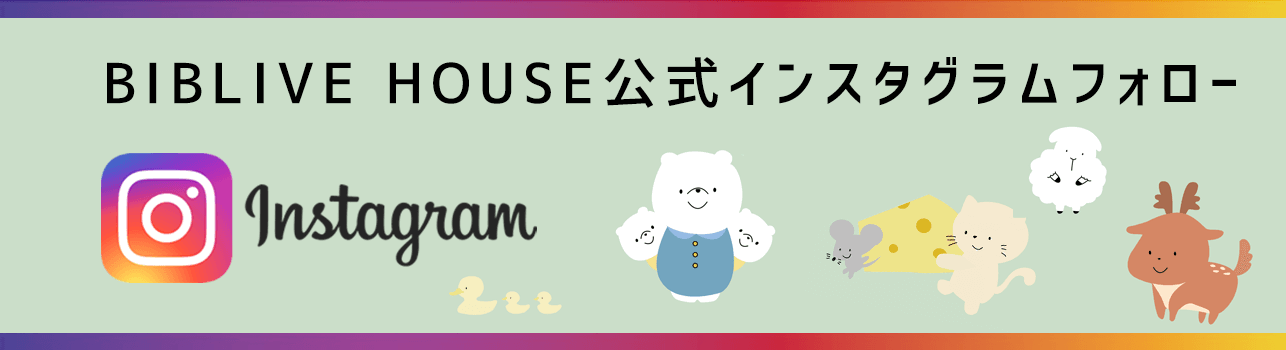ぬるま湯のような環境
今日は欠乏や競争が人にもたらす効果について書きたいと思います。過度な欠乏、競争は負の側面が大きくなりますが、適度な欠乏や競争は人を成長させると思っています。僕の家庭はいわゆる中流階級でしたが、今日食べることに困ったことはありませんでした。
また、教育制度においてもゆとり教育世代ではないですが、平成的な価値観の教育を受けたので、過度な競争というのも経験していません。誰かに尻を叩かれることなく、外圧やプレッシャーの少ない環境にいました。ようはぬるま湯のような環境で育ってきたのです。
競争社会の過酷さと貧富の差
しかし、その考えが変わることがありました。それは2007年に中国に留学に行ったからです。それまで僕は自身がぬるま湯の環境にいることさえ知らなかったのです。当時中国は翌年に北京オリンピックを控えていました。出生率も高く人口ボーナスの恩恵を受けており、国全体の熱気を肌で感じました。その中で競争社会の過酷さと貧富の差の厳しい実情も目の当たりにしました。
当時僕が留学していた大学は中国の国公立だったのですが、凄まじい受験戦争を勝ち抜いた優秀な学生しかいませんでした。みんな小中高と猛勉強し青春は大学にお預けで生きてきたのです。中国では受験戦争があまりにも過酷なので日本に留学して日本の国公立の大学に行く方が楽だとも言われています。彼らの学びに対するハングリー精神や態度は自分が如何に適当に楽して生きてきたかを思い知らせてくれました。
生きるとは
また当時中国は社会保障制度が整っておらず、街を歩けばその日を生きるためにお金を稼ごうとする人がたくさんいました。ある人は何かを売り、ある人は物乞いをし、ある人は歌を歌いながらお金を稼ごうとします。健常者はもちろんのこと、障がい者ですら国が守ってくれないので自分で何とかしないといけないのです。
僕はこの時に「生きるとは」ということに関して教えてもらったように思います。なぜなら、僕はこれまで日本は社会保障制度もあるし、生活保護制度もあるから、心の中でどこか「なんとかなる」や「国が助けてくれる」と思ってしまっていたからです。
どのような環境であっても
しかし、実際生きるということは僕が中国で目の当たりにしたように過酷なことなのです。これからも未来永劫、国が守ってくれるというのは一種の宗教的考えであり日本教だと思います。実際、そのような制度は戦後人口ボーナス下、高度成長下にできた制度で、まだ80年しか経過していません。少しレンジを100年にすると、戦中の過酷な時代が見えてきます。
僕自身が思っていることは、どのような環境であっても生きられる力を今のうちに身に着けておくということです。