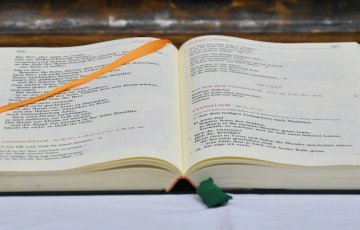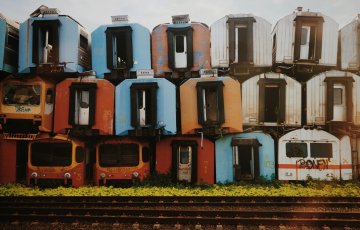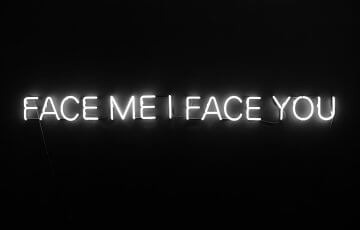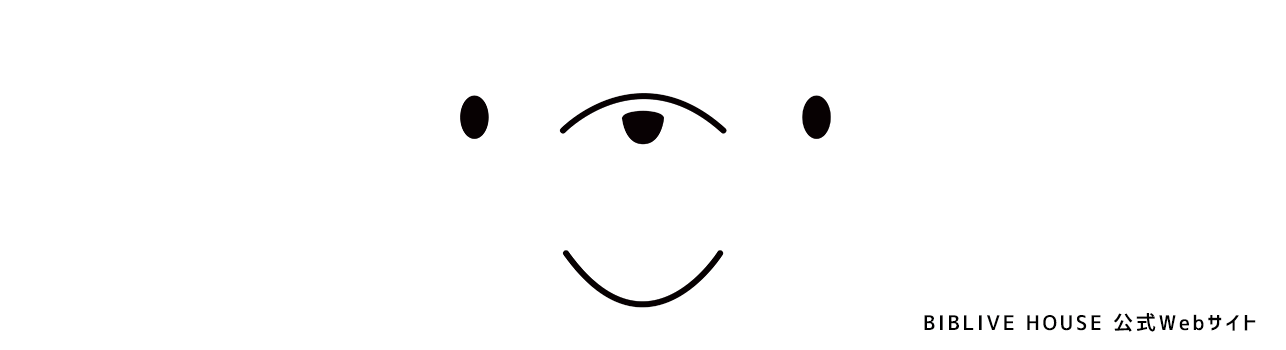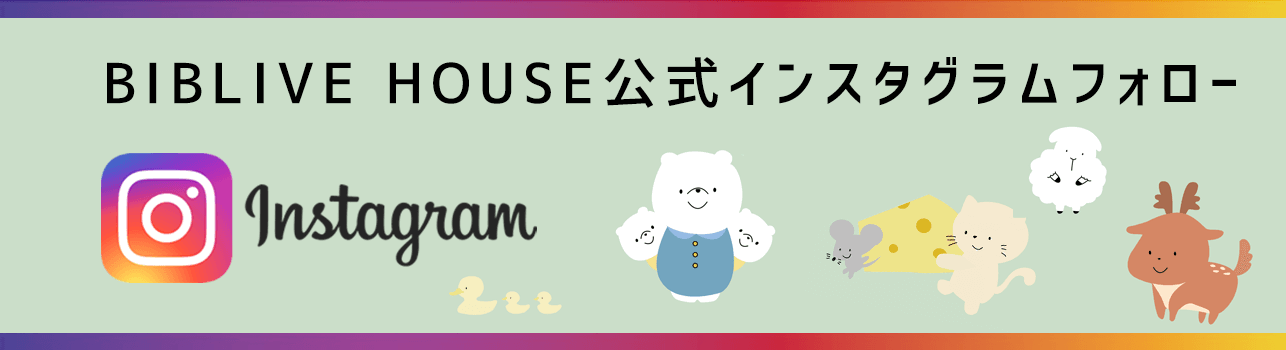ある種の高等なフィクション
ある弁護士の方がこのようなことを書いていました。
「衣食住足りてそこそこの満足感のある状態のなかでハングリーな気持ちを高めることは、ある種の高等なフィクションであり、よほどの強い克己心・向上心・自律性・問題意識を備えていないと非常に難しい。」
僕自身は衣食住に困ったことはありません。しかし、衣食住が足りていても、ハングリーな気持ちが高まったことがこれまで3回ありました。1回目は浪人していた時期、2回目は退職した時期、3回目は中国から帰ってきた時期です。
それぞれの時期に共通することは「レールから外れている」ということです。その時期には「社会的に私は何者なのか?」を証明してくれるものを全くもっていなかったのです。クレジットカードの審査に落ちるほど社会的信用がありませんでした。
ハングリーな気持ちが高まったとき
しかし、そのような状況においては自然とハングリーな気持ちが高まったと思います。なぜなら、当時自分は社会から外れてぽつんと存在しているような孤独感を感じていたからです。だから、なんとかして「社会的に何者かになりたい」と思っていたのです。そのような一種の焦燥感は僕の内面を研ぎ澄まさせてくれました。そのおかげで、一つのことに異常に集中して取り組むことができたのです。
では、今はどうでしょうか?今は以前に比べたら安定した日々を送っています。それであっても、冒頭で引用したような高等なフィクションが僕を適度な緊張感のある場所へ導いてくれています。その最たるものは目標設定の内容になるのですが、それ以外でも、たとえば「今会社をくびになったらどうするか?」や「自然災害が起きたら?」などの言語は定期的に回してます。
信仰生活におけるハングリーな気持ち
この高等なフィクションというのは、信仰生活にも全く当てはまると思っています。なぜなら、クリスチャンはたとえ一時であれこの世の多くの満たしてくれるものの中で生きています。もし、空っぽをせずにこの世的なものを求めるのであれば、神様に対する飢え乾き(ハングリー)を持ち続けることは簡単なことじゃありません。
では、どうすればいいのでしょうか?信仰の場合は、高等なフィクションは必要ありません。必要なことは主と共に歩むことです。なぜなら、主と共に歩めば、霊的な飢え乾きが起こり、さらに主の心、主の目でこの世界を見ることができ、そこではじめて救霊の飢え乾きが与えられるからです。