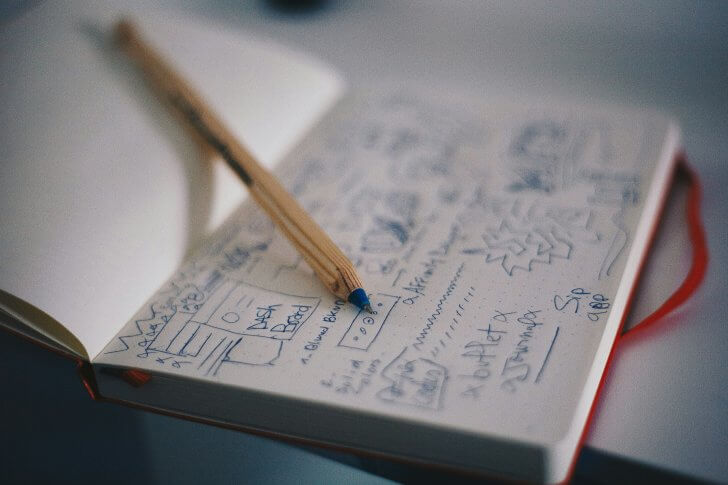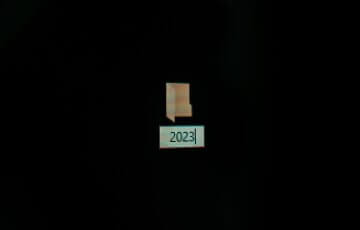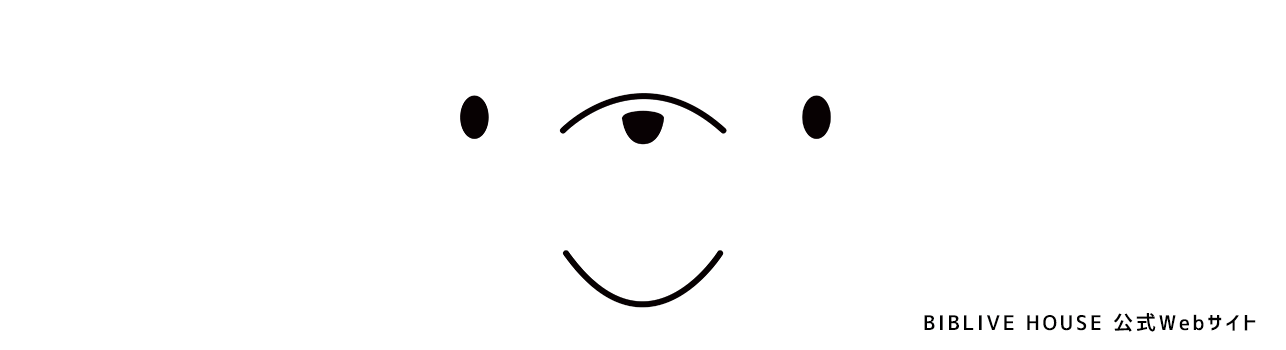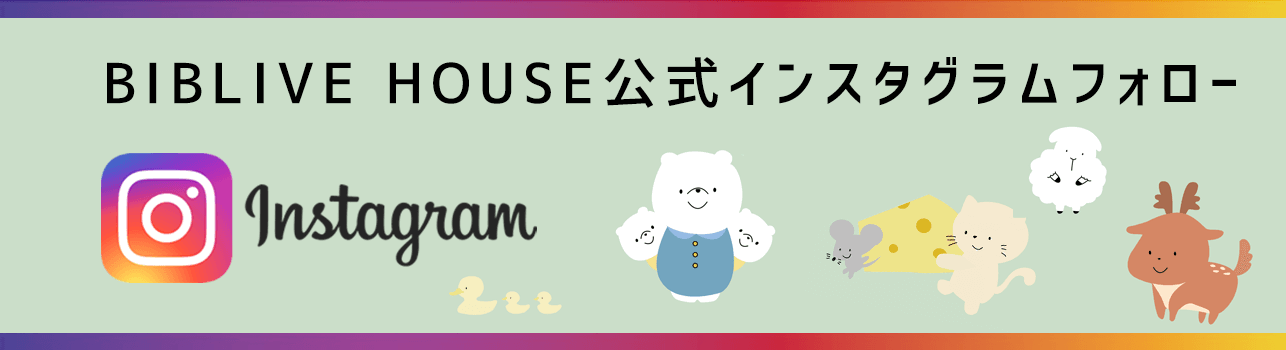すべてに応用可能な原理・原則
昨日は、自分にはデザインセミナーをする資格があるのか?という自問について書きました。その結果、デザインに関して教える資格はないと結論づけました。しかし、僕にできることもあります。それは、「未経験、かつ文系の自分がどのようにデザインやWeb制作を独学で学んできたか?」についてなら語れると思ったのです。
僕がセミナーで語ったことはデザインからはズレているところもありますが、このようなことを書きました。それは、すべてに応用可能な原理・原則を知ること、デザインのテクニック、デザインをする上での姿勢の三つです。
適材適所の原則
原理・原則と書くと大げさですが、三つ語りました。一つは、「適材適所の原則」です。仕事で輝けるかどうかはこの原則にかかっています。なぜなら、仕事に関して言えば、強みを生かして、弱みを無力化するの一言に尽きるからです。僕は新卒で入社した会社は強みを殺して、弱みを生かさないといけない環境でした。それで上司からものすごいパワハラを受けたことはこのブログでも何度も書いてきました。
つまり、デザインを学ぶことは大切ですが、「自分はデザインが好きか?向いているか?」という自問はとても大切だと思いました。向いていないのに、好きでもないのにやり続けるのは原理・原則に反します。
慣性の法則
二つ目は「慣性の法則」についてです。何事でも最初に大きなエネルギーが必要です。自転車に乗るのに最もエネルギーが必要とされるのは漕ぎ始めです。しかし、最初の漕ぎ始めを頑張り、勢いがついてきたなら、あとはわずかなエネルギーだけで自転車は進み続けます。
新しいことをする時も同じです。必ず最初に大きなエネルギーが必要とされます。しかし、そこを乗り切ったら見える景色が変わるのです。これを事前に知っておくことは非常に重要です。なぜなら、しんどいから、いつまでたっても景色がかわらないから自分には向いていないんだと勘違いしてしまう場合もあるからです。
基本の原則
三つ目は、「基本の原則」です。今はAIで誰でもデザインが作れます。簡単なプロンプトで画像を作ったり、レイアウトを作ったりできます。ちまちま、Illustratorでデザインを作りこんだり、Photoshopで編集する必要もありません。しかし、それらは、いわばアプリケーション的なテクニックであって、廃れるものです。
すたれないものは基本です。基本さえ体に沁み込んでしまえば、それが差別化要因となり、強みとなります。デザインの基本とは観察する力です。また「いいデザイン!」と思った時にそれを自問して言語化する能力です。そして、いいデザインを見る習慣を作り、いいと思ったデザインを集めたりすることです。
たとえば、今は簡単に素材がダウンロードできますが、Illustratorでパスでデザインを作る力などはデザインの本質や基本を学ぶことができると思います。僕は、もぐりのデザインをする者ですが、上記原理・原則に従って今があります。